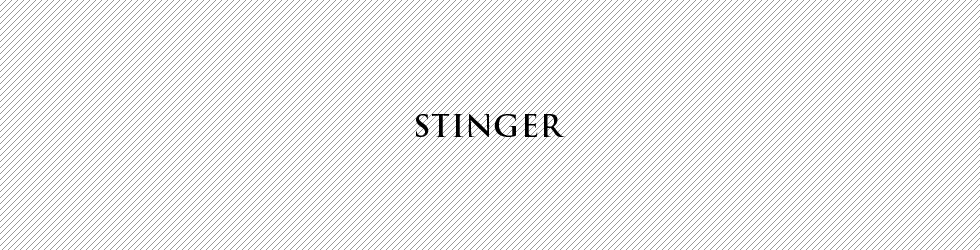「富士山三大噴火」と呼ばれる噴火。実は2大だった可能性も…?
お正月の定番ニュースの一つに、富士山でご来光を拝む登山客の様子というものがあります。映像で見るばかりで、実際にご来光を拝んだことはない私でも、やはりその様子は神々しく、息をのみます。
さて、この富士山、1990年代まで休火山とされていましたが、現在は活火山であることが知られています。富士山が最後に噴火したのがいつか知っていますか。それは、宝永4年(1707年)のことです。地震が起こった年の年号を取り、宝永大噴火と呼ばれています。
かの有名な新井白石は『折たく柴の記』にその時の様子を書いています。それによると、遠く離れた江戸の空も黒い雲の覆われ、雷鳴が轟き、雪かと思ったものは火山灰で、草木の上に火山灰が積もったのだそうです。
この宝永の大噴火は、富士山三大噴火のうちの一つです。その他に、延暦19~21年(800~802年)に起こった延暦の大噴火と、貞観6年(864年)に起こった貞観の大噴火が挙げられています。どちらも平安時代に起こった大噴火です。
延暦の大噴火については面白い研究があります。もしかしたら、延暦の大噴火は三大噴火に含まれるほどの噴火はしていなかったのではないかというのです。その理由として、宝永大噴火では2mにも及ぶ火山灰の堆積が確認できるのに、それが見られないことが挙げられています。【参考1】
もしかしたら二大噴火だったかもしれない、富士山の三大噴火。今年のお正月、テレビなどで富士山を眺めるとき、地面を轟かせた噴火した過去があり、そのエネルギーを内に秘めながらそこで生き続けていると思いながら、眺めてみてはいかがでしょうか。今までとは違った風に富士山が見えてくるかもしれません。
【参考1】
富士山延暦噴火の謎と『宮下文書』
関連記事
-

-
実は富士山よりも危険!?要注意な阿蘇山大噴火。火砕流などが日本全土を覆う可能性も
長野県の御嶽山の突然の水蒸気爆発は、57名という火山噴火最大の死者を出すにいたり …